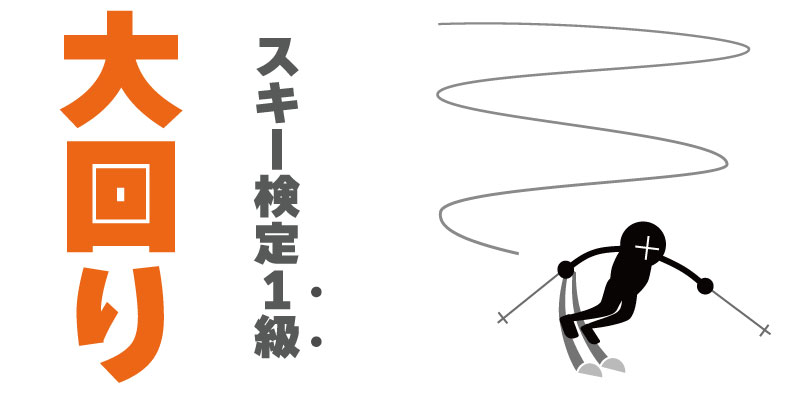
スキー検定1級「大回り」合格に必要な2つの超重要ポイントをまとめました。
この記事を読んでいるあなたはきっと検定合格に向けて努力を続けているスキーヤーのはず。ただ、「大回りってなにを意識したら良いかわかんない!」「検定員は何を見ているの?」そんな疑問が浮かんでいるのではないでしょうか。
簡単そうに見えて意外と掴みどころのない種目、大回り。今回は、スキー検定1級合格2回・すべて大回りで加点合格したスキーヤーが、とっておきの「コツ」をお伝えします。
目次
スキー検定1級の大回りとは
まずは定義の確認です。1級大回りの正式名称は「パラレルターン大回り」、検定の場は急斜面、ナチュラルです。
パラレル=平行ということで、スキー板を平行にしたまま、急斜面を綺麗にすべり降りてくる種目です。ただし、「ナチュラル」と言うからには、綺麗にグルーミングされた斜面とは限らず、午後の荒れた斜面やアイスバーンなんかで検定が行われることもあります。
合格点は70点なので70点以上が合格ということになりますね。
基本的には、文字通り大きく回る種目なので、だいたい、コースの横幅を目いっぱい使って滑るイメージです。
大概のスキーヤーがゲレンデでメインで使う滑りは、この大回りでしょう。誰しもが普段から滑り慣れていると思います。ただ実は、苗場の20-21シーズンデータによると、検定になるとおおよそ50%くらいの合格率のようです。つまり半数は落ちるという意味で油断ならない種目なんです。
スキー検定1級大回りで絶対押さえたいポイント2選
自分の経験をもとに2級までと違うポイントをまとめました。これができるかどうかで合否が分かれるよ!という超・重要ポイントなので真っ先に習得しましょう。
ちなみに僕はこの2つが完璧にできるようになってから、検定の事前講習で「もっとこうした方がいいよー」的なことを言われなくなりました。合否を分けるポイントなので熟読してください!
あ、それと前提としてですが、正しい「ポジション」で滑り続けることが絶対条件なので、正しいポジションをまずスキーの基本姿勢「ポジション」を徹底図解【最重要!必死で学べ】で勉強してから読んでくださいね!
カービングで滑る

2級までと違う最大のポイントはカービングで滑っているかどうかです。
カービングとは、スキー板のエッジにしっかり乗っている滑りのことを言います。ちなみに、カービングの逆はずらし。板が斜面を撫でるように動き「ズザザザー」となる滑りです。
実は2級まではズレを伴う滑りもOKでした!2級の大回りは「基礎」パラレルターンと呼んでいたと思います。基礎と付くときは基礎的な滑りなのでずらしを使っても安全に滑ればOK、でも「基礎」が抜けた1級のパラレルターン大回りでは、キレがあるスピード感のある滑りが求められます。
ちなみに、カービングとずらしの違いですが、滑った跡を見ると一目瞭然です。カービングで滑ると2本の深いライン(溝)がくっきりと綺麗に残ります。対してズレの多い滑りは半月状の跡がうっすら残ります。
では、どうしたら綺麗なカービングができるのでしょう?
カービングのコツ

まず結論から。板に対して垂直方向に体重を乗せて、じんわりとスキー板を押しこみましょう。
実践的には、ターン外側の腰を出していきながら雪面をグーッと押していくイメージです。なぜ押すのかと言えば、スキーを押すことで雪面に板が固定されるからです。そして押す量が多ければ多いほど雪面に板がガチッと食い込み、強固に固定されます。固定されたらあとは体重を乗せて滑っていくだけです。
つまり、自分から積極的に板を押していく滑りが求められるということです。滑った跡を見ればきっと綺麗な2本線が現れていることでしょう。
さて、たったこれだけのことですが、なぜできないのでしょうか?
考えられる理由は、正しい方向、つまり垂直方向に体重を乗せることができていないから。例えば空手の瓦割りでは、真上から拳を振り下ろさない全部の瓦は割れません。これって、せっかく力を掛けようとしているのに上手く力が伝わっていないってことです。
実際ゲレンデでよく目にするミスケースは、腰が外れた滑りです。腰で「く」の字に折れ曲がっているスキーヤーを見かけますが、残念ながらこれでは正しい方向に力が入りません。
正しいカービングのためのトレーニング

しっかり体重を乗せていくために体の動きを矯正するトレーニングがあります。僕もシーズン始めなんかに実践していますので、よろしければあなたもやってみてください。
①レールターン
まずは、体を1本の棒だと考えてターン中もまっすぐ立ちます。そのままレールターンをしていきましょう。レールターンとは、体をまっすぐ1本の棒と考え、両スキーのエッジを雪に噛ませてながら、エッジからエッジに移動しながら滑る滑りです。頭が左右に揺れるイメージですね。
②外向傾に寄せていく
レールターンが出来たら次は、ターンのタイミングで外向傾(体が弓なりになる姿勢)を意識していきます。綺麗な外向傾は、腰から「く」の字に無理に曲げるのではなく「肩を地平線と平行に近づけていくこと」を意識しましょう!あわせて、足首・ひざ・股関節を少し曲げていくと、自然と体が弓なりの姿勢になってくるはずです。これが程よい外向傾です!
③重さを乗せる
最後に、ターンのタイミングで外スキーに体重を乗せていきます。ターンに入る時から、思い切ってグーッとスキーを押しながらターンしてみましょう。エッジを噛ませながら、肩の水平ラインをグーっと下方向に押しこんでいくイメージです。②の外向傾が出来ていれば、問題なくスキーを押し込めるはずですよ!
このようにスキーを押し込むことで、たわんだスキー板に逆に押し返される感覚が分かってくると思います。この反発力を上手く次のターンに繋げていくことが大切!なのですがここら辺は次のポイントで見ていきましょう。
・外向傾:スキーの正しい姿勢「外向傾」を完全攻略せよ!【初心者必見!イラスト講義】
体重移動と体の動きを意識する

超重要ポイント2つめです。1級以上に必要な「ターン前半」を仕上げ、綺麗なターン弧を描くために体重移動と体の動かし方も必ず意識しましょう!
具体的には、①体を下側に落下させていく動き、②低い姿勢でスキーを押さえる動き、③立ち上がる動きが必要になってきます。
この3つの動きを、確実にかつスムーズに繋げていくことで合格点に近い滑りが実現できてきます。
さあそれでは、ひとつずつ、解説していきます!
①体を下側に落下させる動き

これが一番重要なポイントとなります。
この動きができるようになると、1級以上に求められる「ターン前半」が上手く作れるようになります。前半が作れる=綺麗なターンが完成すると思っていただいて結構です!
意識としては、そろそろターンしようかな~と思ったタイミングでエッジを踏み込みながら、体を下に落とし込んでいきましょう。
倒れる方向としては、スキー板が向いている方向より45~60度くらい内側に向かって倒れこんでいきます。スキー板の進む向きを少し先取りして体が動いていくイメージですね。
ちなみによくプロスキーヤーがターンするときに体のラインがかなり倒れているのを目にしませんか?この「倒れる角度」ですが、滑走スピードによって異なります。
つまり、スピードが上がれば上がるほど滑っている方向(外向き)に働く慣性が働きます。その力に耐えるために、体を内側に大きく倒して耐えているわけです。逆に言うと、スピードが遅いのに体を倒しすぎていると「無理な体勢だなー」と思われます。なにごとも、ほどほどで…!
この体の倒しこみができるようになった頃には、「ターン前半をとらえる」という技術が完成しているはずです。
まあ、だいぶ簡単に言っていますが、体を下に落としていくのって、初めは結構怖いんです。ただ、カービングの箇所で触れたように、板のエッジを踏み込むほど足場が安定します。きちんとスキー板を踏めていれば、下方向に体重をかけていっても転倒することはありません。安心して倒れこんでみてください!
②低い姿勢でスキー板を押さえる動き

カービングターンによって生まれた推進力を前に進む力に変えていくために必要な動きです。体重を乗せてターンをすると板の反発が生まれ、押し返されます。この推進力を活かして滑っていきましょう。
ターン終了後、横移動の時間が生まれると思います。この時間帯では、足首・ひざ・股関節を曲げた体勢を維持してください。
この時、ターンによって生まれた圧をしっかり活かすためには、両足で板をグッと押さえつけていることが重要です。ここで押さえつける力が抜けてしまうと、板にたまった推進力が上にスポンッと抜けてしまうんです。
なので低い姿勢で板を押さえつけながら横方向に移動しましょう!ターン終了後、次のターンへの移動区間の前半はグッと押さえつけ続けます。
ちなみに、板を踏み込んだ時の反発(推進力)が大きいと体が遅れがちになります。そうなると後傾になり、思い通りの操作が難しくなってしまうので、スネをブーツの前側に押し付けておくイメージを持つと良いでしょう。慣れてきたら足の真ん中(土踏まず)で板を押さえるイメージに移行していきましょう!
③立ち上がる動き

いよいよ最終段階です。いわゆる「ニュートラル」というポジションを作ってから次のターンの準備をしていく動きです。
低い姿勢で板を押さえつけている姿勢からポジションを元に戻します。足首・ひざ・股関節を少し緩めるように意識すると自然と力が抜けるはずです。
さてここで、大回りで重要な「ニュートラルポジション」を作ります。ニュートラルとは、両足のスキー板の裏面すべてが斜面に対してピタッとくっついていることです。つまりエッジが立っていない状態とも言いますね。
ターンから次のターンへ移行していく間、このニュートラルな区間を2mほど取るようにしましょう。この区間を取るかどうかでターン弧が綺麗なS字に仕上がるかが決定するので習得は必須です。
そして斜面の端まで来たらあとは①に戻り、体を倒していく動作を行ってください。あとは①~③を繰り返していきます。
外足から両足(ニュートラル)、逆側の外足へ、というように体重を乗せていく足は滑りの中で刻々と変化していきます。なので大回りでゆったり滑っているように見えても体は常に動いている感覚です。
右足から両足を経由して左足へ、そして左足から両足を経由して右足へ。この移動を滑らかに、自然にできるようになれば1級合格は確実に近づきます!
そのほかに意識すべきポイント
基本的には、カービングターンと体の動きを途絶えさせないことの2点を意識して滑れば合格点は取れます。ただ、それ以外にも意識していただきたいポイントがあります。全部で3点あるので、サラッと触れておきましょう。
ターンマックスで足は伸ばし切らない
ターンの一番外側で足を伸ばし切らないよう気を付けてください。ひざの曲げをある程度維持しておくことで、雪面とやり取りすることができます。
というのも、斜面状況によりスキーを押す量を強くしたり、逆に柔らかく押したり…そんな調整が必要になってきます。ここで足を伸ばし切ると「ゆとり」がなくなってしまい流動的に動けなくなってしまうんですね。
腕は広めに構える
腕は広めに構えましょう。イメージとしては新聞紙を広げて読んでいる感じです。腕を広げることで肩のラインを調整してバランスを取りやすくなります。
また、大回りでは基本的にストックを突く操作は不要です。ストックを突くとその分動きが遅れてしまい、スムーズな動きが阻害されてしまうんですね。突く癖があるスキーヤーの方は注意してください!
絶対的外足荷重
スキーの絶対的なルールは外脚荷重です。
ターンでスキーを押していく時も外脚で押していく感覚は維持してください。ちゃんと外脚で滑れると、きれいな弓なりの外向傾が自然と作れるようになります。「外脚命!」この言葉を胸に刻み込みましょう!
斜面状況に合わせた滑り方
スキー場の雪質は毎時間、刻々と変化します。午前中と午後では全く違う状況…なんてことも多いです。なので「大回り」ひとつ取っても斜面適応力を上げていくことが重要です。このパートでは、多くのスキーヤーが苦手とする2大滑りにくい斜面「アイスバーン」と「もこもこ斜面」について解説していきます。
アイスバーン
斜面が凍っているので、エッジが噛みにくいシチュエーションです。
特にエッジを研いでいない板ではターンの際に踏み込みすぎると板が外れてしまいます。なので外向傾「強め」で踏み込む力は「弱め」で滑ることをイメージしましょう。また、切り替えではできるだけ低い姿勢を維持します。通常よりも低い姿勢を保つことで板が斜面に噛まず外れたときの軌道修正もしやすくなります。
そして、スキー場の特性として、斜面の両端に雪が溜まる傾向があります。なので真ん中はカリカリでエッジが立たないけど、斜面の両端はエッジが効く、という状況が多いです。そんな時は端から端まで大きく使って、可能な限りエッジが噛む場所でターンすることをおススメします。
モコモコの悪雪
多くのスキーヤーが滑った後の午後の斜面に多いです。もこもこしていて足を取られやすいという意味では、アイスバーンと同じくコントロールしにくい状況です。
そんな時は、出来るだけ関節をクッションのように柔らかくして雪面から受ける衝撃を吸収しながら滑ることを意識しましょう。そして、このような転倒しやすいシチュエーションでは、外向傾を「強め」で滑ってください!
まとめ
大回りは一見、斜面を広く使って大きくターンしていくだけですが、意外と動きの要素が多いのが特徴です。
個人的な感覚としては、滑り出しからゴールまで常に体のどこかしらの部位を動かしています。そう、とっても忙しい種目なんです。体を落とし込む・板を押さえる・ニュートラルを作る。この3ステップの動きに加え、スキーを押す・外向傾を作るというカービング要素が入ってくるので複雑なんですよね。
まずは、ひとつずつの動きを意識して練習してみましょう。個々の動きを繋げて何回も滑り込んでいるうちに、意識しなくてもスムーズにできるようになります。それでは1級合格目指して頑張りましょう!




